雑誌や広告業界の第一線で、フォトグラファー・ビデオグラファーとして活躍する大石祐介さん。小学生の頃にNBAと出会ったのをきっかけに、アメリカのストリートカルチャーに傾倒し、バスケットボールやダンスに明け暮れる青春時代を送っていたといいます。
大石さんが本格的に写真を撮り始めたのは28歳の頃。体調を悪くした際にリハビリのつもりでカメラを持ったのがきっかけでしたが、東京で出会った人たちとの繋がりから仕事を依頼される機会が増え、活動10周年を迎えた今年、これまでに撮りためてきたニューヨークのローカルなライフスタイルをまとめた初の写真集『LIFE THROUGH MY EYES』を発表しました。
「何かに特化してなくたって、普通の人だって何でもできるよ!」と語る大石さんに、本気で遊ぶことで得られた損得勘定抜きの人間関係や、様々な人とカルチャーが交じり合っていた札幌のストリートシーン、〝世代を超えた人々が交わる場所〟を作りたいという函館への想いなどについて伺いました。
全5回でお届けします。
取材・文章:阿部 光平、写真:馬場雄介、イラスト:阿部 麻美 公開日:2018年6月6日


「普通の人間でも、何でもできるよ!」ってことを伝えたい
━━今は東京の最前線でバリバリと仕事をされていますが、今後も東京を拠点に活動していくつもりですか?
大石:漠然となんだけど、2020年の東京オリンピック終わったら、函館に帰ろうってのはずっと思ってて。去年とかは、帰る気満々で、函館でこういうことやろうとかも考えてたんだけど。今は、もうちょっと時間かかるのかなとか思ってて。
━━「もうちょっと時間かかる」っていうのは?
大石:函館にいない人間がこういうこと言うのは、住んでもいないし、現状を理解もしてないし、「はぁ?」って感じかもしれないけど。俺が客観的に見た今の函館が、なんて言うんだろ…、若い子たちが遊べる場所だったり、ひとつのカルチャーが発展しそうなまとまりだったり、そういうのがあまり感じられないなって思ってて。そういうものを作れたらなって思ってるんだけど、今、急にそれをやったところで、上手くいく可能性が見えないっていうか。
だから、今度、初めて写真集を出すんだけど、そういうのを通じて自分の存在を知ってもらって、こういうことやってる函館出身の人間がいるっていうのを、もうちょっと函館の人に知ってもらいたいなって。そういう自分がやってきたことで、函館の中学生、高校生、大学生とか、20代前半の若い子たちとかに、いろんな可能性を感じてもらえたら嬉しいなって。
━━写真を仕事にすることなんて想像すらしてなかった人が、第一線で活躍しているという姿には、若い子の背中を押す説得力があると思います。
大石:大人が「なんだあいつら! やべーな!」っていうような若い子が出てきてほしいなって思ってるんだよね。函館で。その地盤を固める作業をちょっとでも、自分が関わることできたらなって思ってるんだけど。それを外から、ちょっとずつ、ちょっとずつやって、面白いことができそうってなったときに、函館に帰りたいなって。
そのためにも、今はもっともっと自分のことを知ってもらわなきゃなんないから、こっちで活躍して、名前を知ってもらえるような活動をしていかなきゃいけないのかなって思ってる。
━━もっと、自分自身のインパクトを大きくしたいって感じですかね。
大石:そうだね。だから、自分の仕事が誰にでもわかるような状態になったら、一番嬉しいかな。今やってる仕事も、もしかしたら「おぉ、スゴイじゃん」って言ってくれる人もいるかもしれないけど、撮った写真を通じて自分のことを直接知ってくれる人はなかなかいないから。
━━「自分の仕事が誰にでもわかるような状態」に持っていくために、具体的には、どんな仕事をしていこうと思っていますか?
大石:それは、仕事をくれる人たちとの関係もあるからね。俺がこういうことやりたいって思うものを、全部やれるわけではないので。だから、やれることだよね。「こういう写真を撮れるようになろう」とか、「こういう映像を撮れるようにしよう」とか、今自分でできることを続けていった結果、面白い仕事なのか、大きい仕事なのか、そういうことに繋がっていけばいいなって。
それができれば、今度は函館にも面白いことを持って帰れるだろうし、東京で繋がりがたくさんできたので、〝俺がいる〟ってことで、面白い人が函館に来てくれるってことも実現できるだろうし、そういう関係性ももっと深めたいなって。
━━写真集を出すのも、函館に対して何かを還元したいという想いの延長なんですか?
大石:写真集は一個の形。東京で出会ったフォトグラファーの先輩が、「報道でも、スポーツでも、対象が何であれ、それを写真に撮って、どこかに掲載されればカメラマン。フォトグラファーは、1枚の画で勝負できる人。本を出して初めて写真家だ」って話してたのが、ずっと頭に残ってたんだよね。
━━フォトグラファーは、世の中に自分の作品を出して、ようやく一人前だと。
大石:だから、本はやっぱり1回出したいなって。作品をひとつでも残せば、もし写真を撮らなくなっても、「俺、写真やってたんだ」って言えるかなって。そのくらいの感覚でやってたんだよね。とりあえず10年って節目にもぶつかったし、あとは名刺代わりにもなるかなって。
仕事では別に何でもやるけど、自分の撮りたい写真はこっち。そういう使い分けはしてるかな。何をするにしても、チョイスは全部自分だから。この人に会う、この人と喋る、仲良くなる、撮るとか、全部見極めるのは自分でしょ。だから、選択することが人生で一番大事なことかなって思ってる。
━━何かを選択する上で、一番大事にしてる判断基準はなんですか?
大石:直感はもちろんあるよね。でも、それだけじゃわかんないこともいっぱいあって、第一印象が悪かった人でも、話すとめっちゃいい人だったってこともあるし、その反対も。
だから、最終的にチョイスの判断基準は、やっぱりコミュニケーションをとった上で、自分にとっていい方向に進んでいけるかどうかってところかな。

[写真元: MARCOMONK]
━━写真は一生続けていこうと思っていますか?
大石:撮るってことは、辞めないと思う。だけど、ずっと写真で仕事していくかっていったらわからない。
かっこいい人も、すごい人もいっぱいいるし、街を歩いてて看板見たり、本屋をフラついてるだけでも、「世の中には、こんなにフォトグラファーがいるのか」って思うし。俺なんて、そんな大勢の中のただのひとりだから、いつ消えたって、別に違う人が出てくるからね。
━━もっと上に食い込んでいきたいとか、唯一無二の存在になりたいみたいな気持ちはあまりないんですか?
大石:うーん、欲がないからね。売れたいとかよりも、人の役に立ちたい。
━━仕事のオファーをしてくれる人が、喜んでくれる結果を出したい?
大石:その先だよね。仕事くれる人じゃなくて、撮ったもので喜んでくれる人たちがいるんだったらやりたいし、それが写真じゃなくてもいいと思ってる。仕事はね。
写真はずっと撮ってくっていうのは、好きだから。作品とかはたぶん残していくとは思うけど、自分がやってることが、例えば函館のためになるんだったら、別に写真じゃなくても、映像じゃなくてもよくて。どの道、写真は撮るからさ。
━━表現としての写真は辞めないけど、それが仕事じゃなくてもいいと。
大石:簡単に言うとさ、芸能人とかスポーツ選手とかって、少なからずいろんな人に影響を与えてるでしょ。俺もジャッキー・チェンとか、マイケル・ジョーダンから影響を受けたし。そういう出会いって、若い人にとって、ひとつのきっかけになると思うんだよ。
━━はい。
大石:俺は別に、芸能人とかスポーツ選手になりたいわけじゃないんだけど、「函館出身で、こうやって写真で食ってる人がいるんだ」とか、「この写真スゲー素敵だな」とか思って、「俺も写真撮りたい!」って言ってくれる人が現れたりとか、そういうきっかけ作りをしたいと思ってるの。
仕事で上手くいくよりも、函館の若い子たちが何かアクションを起こすきっかけを作って、どんどん面白いやつが出てきてほしいなって。その結果、「函館って面白い街だよね!」って言われたり、外でも「函館出身です!」って胸を張れるような街になればいいなって思ってる。そうやって、函館に還元できるようなことをしたい。
━━その函館愛は、どこから来てるんですかね?
大石:やっぱ、育った街、好きでしょ。理由って、あんまりないかもしれない。「いや、好きなんだよね」っていう。
自然があるからとか、こういう店があるからとかでもなく、人だって面倒くさいやつ多いし(笑)。でも、その面倒くささの中にも、どっか心地よさがあったりとかさ。
━━わかります(笑)。
大石:たぶん、俺が「函館で若い人のきっかけ作りをしたい」って言ったら、面倒くさがる人もいると思うんだよ。「東京に出といて、なんだよ急に」って思う人もいるだろうし。
でもね、そこすらもちょっと巻き込みたいなって。「防御力ある方なんで、どんどん打ち込んでください」って(笑)。

大石:やっぱ、元気ある街って、若いやつが元気なんだよ。俺らが元気だしたところで煙たがられるだけだから、どっちかっていうと裏側に回って、若い人たちをサポートできる状況を作れたらなって。
それが具体的に何かっていうとスゲー難しいんだけど、いろんな人が遊べる場所だったり、カルチャーが生まれる場所だったりするのかなって。
━━場所作りかぁ。
大石:例えば、「今は夜にクラブで遊ぶ時代じゃない」とか、「函館はクラブも、そんなに人が入らないよ」とかって言うなら、別に「クラブで遊ぼうぜ!」って言う必要はなくて。そうじゃなくて、夕方から夜にかけて遊べるような場所を作って、そこにDJがいて、本とかもいっぱいあって、月に1回オシャレして行くような場所は、どうだろうとか。
そういう場所があると、新しい音楽やカルチャーとも出会えるだろうし、服も買うようになるだろうし、世代を超えたコミュニケーションも生まれるだろうし。だから、誰でも来れるような場所を作りたい。仲がいいから集まるっていうんじゃなくて、そこに行けばいろんな人と繋がれるって場所を。ハブかれてるようなやつもひとりで来いって。俺が相手してあげるからって。
━━大石さんが函館にいたときって、そういう場所はありました?
大石:どうなんだろう。18くらいのときは、何も考えてなかったからな。でも、古着屋だね。『ヌーディーズ』とか、『ソーダポップ』とか。
━━僕らのときもそうでした。古着屋とか、ライブハウスとか。
大石:ただ、俺は古着屋に行っても、バイトしてる同級生とかとばっかり喋ってて、そこのボスとは、あまり喋らなかったな。
当時の古着屋の人って、かっこよさはもちろん、いい意味での恐さもあったからさ。その近寄りがたい雰囲気も大事だと思う。だけど、人ぞれぞれに合った役目ってのがあるじゃん。だから、俺は恐さのあるかっこいい人ではなく、「あのおじさんに会いにいこう!」って気軽に思ってもらえるような、街のおじさんになるのが理想だな(笑)。
━━街のおじさん! そのイメージは、今すぐにでも湧きますね(笑)。
大石:でも、難しいんだよ。今の若い子たちが、どういう考えを持って、どういう遊び方をしてて、何が好きかってのは、函館から伝わってくるものが全然なくて。函館の人たちに聞いても、みんなわかんないって言うし。それって結局、若いやつらと交流してないってことなんだよなって思って。世代ごとにおもしろいことは起きてるはずなのに、交わる場所がないっていうか。
良くも悪くもだけど、東京って世代の垣根を越えて、面白いものは面白い、良いものは良いって認められる街だなと思ってて。俺も、そういう中で、上の世代の人たちからフックアップしてもらったし。「あいつ面白いから、一緒に仕事してみようよ」って。
━━確かに、東京では仕事でも遊びの場でも年齢を気にする場面っていうのは少ない気がしますね。
大石:田舎だとやっぱりちょっと上の先輩がいて、その人たちに気を使って、若い人がやりたいようにできないことも多いのかなって。その緩和じゃないけど、そうじゃないよっていう環境になるといいよね。
そのためには、下から歩み寄ってもらうのを待つんじゃなくて、歳を重ねてる人たちから歩み寄るべきだと思うし、そうやって同じ目線でいろんなことできるようになったら、もっと面白い街になるだろうなって。だから、今は知らない世代ともっと喋りたいし、仲良くなりたい。
━━世代ごとにまとまるのは簡単だけど、それだと先詰まりになっちゃいますもんね。
大石:俺は、「普通の人間でも、何でもできるよ!」ってことを伝えたいの。何かに特化してないやつでも可能性はあるっていうことを。目立つ存在じゃなくても、バケモンみたいな才能がなくても、バスケ部をクビになったって、面白いことができるぞってのを伝えられるようになりたい。
さっき、「人のためになることやりたい」って言ったけど、偽善ぶってるわけでもなんでもなくて、人に喜ばれるんだったら、もうそれでいいやって思ってて。自己愛があんまりないからさ、俺。だから、残りの人生は、お世話になった人とか街への恩返しをしたいなって。うん、最後にいいこと言ったな(笑)。
━━とても説得力のある、いい話を聞けました。ありがとうございました!
大石:8割ウソだよー(笑)!
SPECIAL THANKS
CONTE-NU
MY FAVORITE SPOT
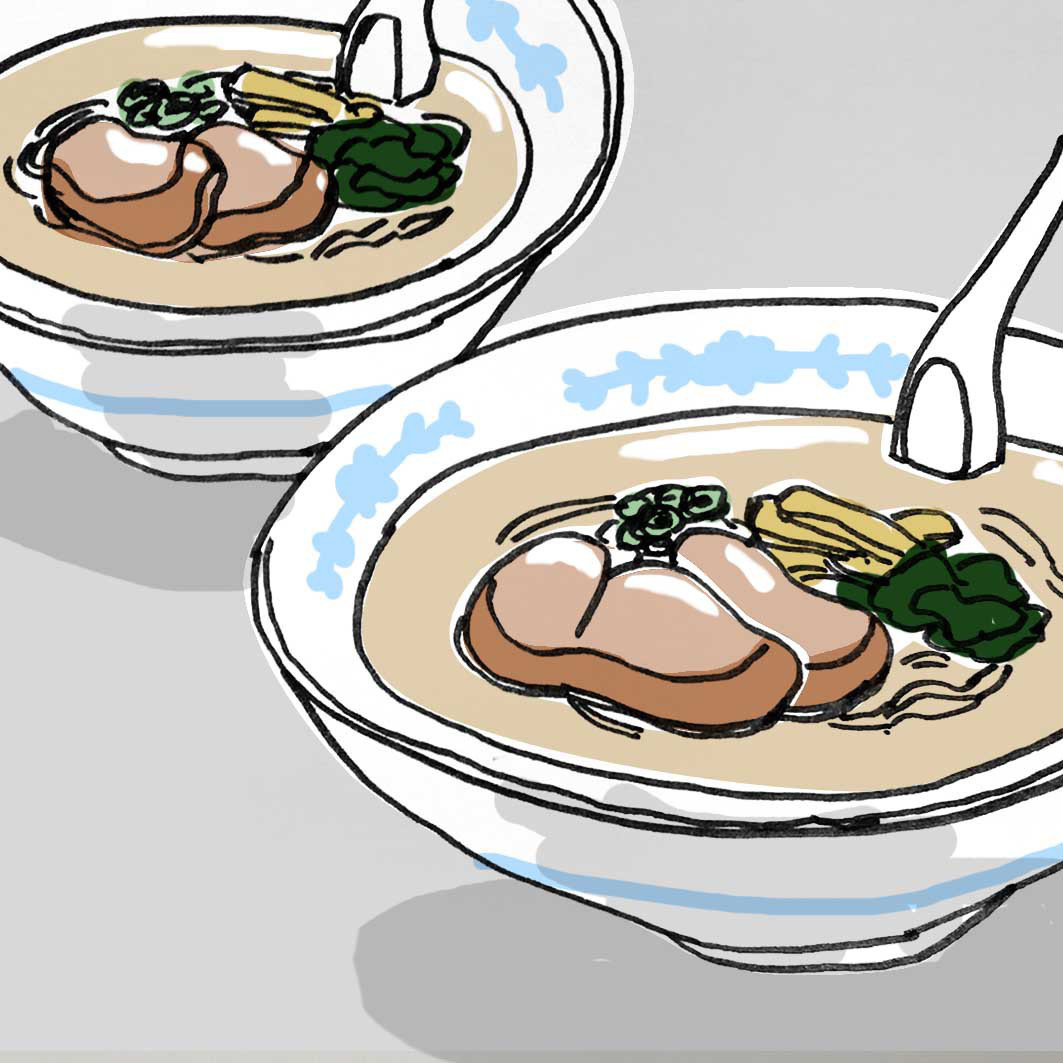
もうないんだけど、桔梗駅の横にあった『孔雀』っていうラーメン屋。今でも俺は、1番のラーメン屋だと思ってる。日曜日の部活終わりにラーメン食ったり、家族でも晩めし食いに行ってたな。

アメリカの4大スポーツのアイテムを扱ってた店。店内にはNBAとかNFLとか、輸入版のビデオが流れてて、ジョーダンの等身大パネルがあったり、スタジャンとかが売ってたりしてて、もう夢中になって通ってた。自分のルーツになった場所だね。

よく遊びに行く友達が連れてってくれるカレー屋。無水カレーってのをやってるんだけど、もう単純に美味しくて。店主の奥さんがもともと仲良くて、函館に帰ったら絶対に行ってるね。




