90年代前半に函館市内の映画館が相次いで閉館したことを受け、フランス映画などの自主上映を行っていた団体が立ち上げた『シネマアイリス』。
映画を愛する函館市民約470名からの出資によって開館が実現したことから、今も〝函館市民映画館〟という看板を掲げている。
2010年には、同館の菅原和博代表が企画し、市民から制作費などの協力を募って、函館出身の小説家・佐藤泰志の『海炭市叙景』を映画化。
その後も、映画館と市民が協力して、佐藤泰志の小説を原作とする『そこのみにて光輝く』、『オーバー・フェンス』といった映画作品を発表してきた。
そんなシネマアイリスは、2016年に開館20周年記念作品として佐藤泰志の初期代表作である『きみの鳥はうたえる』の映画化を発表。
監督には、「まだ青春から遠くない若い監督」として、1984年生まれの三宅唱監督が抜擢された。
2018年8月に公開された『きみの鳥はうたえる』。
僕がこの映画を観たのは、劇中と地続きになっていると錯覚しそうな夏の終わり頃だった。
映画を観ている間、僕は主人公の3人と一緒に気だるくも眩しい日常を過ごしている気分を味わっていた。
見慣れた故郷を舞台に、身に覚えのある刹那的な日々が映し出される物語への没入感は深く、上映が終わって館内の電気がついた瞬間、自分だけがスクリーンの外に置いていかれたと感じたほどだった。
シネマアイリスを出ると、そこには3人の若者が暮らしていた街が実在していた。
なんだか無性に、函館と映画のことが愛おしく感じられた。
夏の函館を舞台にした作品を、まだ暑さの残る函館で観ることができたのは本当に幸福な映画体験だったと思う。
スクリーンの中で観た函館は、確かに僕が知っている街並みだった。
しかし、僕の目に映る函館は、あんなに美しく、儚い街には見えていないことにも気がついた。
「映画監督の目に、函館の街はどう映ったのだろう?」
そんな想いから、三宅監督にインタビューを申し込んだ。
文章:阿部 光平、写真、Webデザイン:馬場雄介、 公開日:2018年12月31日


━━三宅監督、はじめまして。今回はインタビューを受けていただいて、ありがとうございます!
三宅:いえいえ、映画について話すことはあるけど、函館について話すことは少ないので、声をかけてもらって嬉しかったです。
━━そう言ってもらえると嬉しいです。三宅監督は札幌の出身ということですが、映画を撮る前にも函館へ行ったことはありましたか?
三宅:それが、なかったんですよ。小学生のときに、サッカーの遠征で全道のあちこちに行ってたけど、道南はほとんど来れてなくて。函館は、今回の撮影まで来たことがなかったんですよね。
━━じゃあ、『きみの鳥はうたえる』のロケハンで来たのが初めてだったんですか?
三宅:そうなんですよ。シネマアイリスの菅原さんと初めて会ったのが2015年2月の新宿で、そのときに「実は函館に行ったことないんです」って話をしたんです。それで、一度案内してもらうことになって。
━━はい、はい。
三宅:そのとき、函館空港に菅原さんが迎えに来てくれて、最初に車から降りたのが『函館どっく』の方の倉庫がいっぱい並んでるあたりだったんですよ。『海炭市叙景』のロケ地っぽいようなところ。たぶん、菅原さんが最初に見せたかった函館の風景だったと思うんですけど。
━━あぁ、なるほど。
三宅:そこからいろいろと市内を回ったんですけど、最初に「あれ?」って思ったのは、『函館市文学館』に行ったときで。
━━「あれ?」っていうのは?
三宅:函館市文学館へ行った一番の目的は、『きみの鳥はうたえる』を書いた佐藤泰志さんの生原稿を見ることだったんだけど、いろんな展示を見ていく中で、「函館って、めちゃくちゃ都会だったんだ」っていうのを知ったんですよ。国際的な都市だったんだなって。
━━幕末に開港して、外国から様々な物や文化が入ってきた街ですからね。
三宅:そうそう。知識としてざっくりは知っていたものの、具体的なあれこれを初めて知って。例えば、「長谷川兄弟すごすぎるぞ」と。家の中では家族が英語名で呼び合っていて、しかも、子どもたちがみんな作家や画家として大成していった一家があったなんて初めて知ったんですよ。「『丹下左膳』の原作の林不忘=長谷川海太郎は函館か!」って。100年前に、そんなにモダンで文化的な家庭があった街だったってことにビックリしたんですよね。
━━確かに函館には、今も続く名家みたいなところもあるんですよ。
三宅:ですよね。来る前は、疲弊するイチ地方都市というイメージもあったんですけど、もともとは物凄い都会だったんだと思うと、街の見え方も変わってきて。そういう名残りみたいなものを感じたり、探すようにして歩いてましたね。
あと勝手に、同じく港町のリスボンとか高雄とか、そういう他の街のイメージも思い浮かべてみたり。リスボン行ったことないけど。
━━(笑)。

三宅:あとは、やっぱり人が面白かったですね。菅原さんをはじめ、50代、60代、70代の人たちと話すことが多かったんだけど、本業の他に実はバンドをやってたりとか、やたらカッコイイ音楽をかけながら酒を飲んでたりとか、すごく楽しそうにしてる人が多くて。そういうのを見て、「いい感じだなー」と思いましたね。
━━『きみの鳥はうたえる』のパンフレットでは、原作のことを「仕事がないとか大変なことはあるけどそこで人生の喜びを投げ出さずに、映画を見たり、本を読んだり、音楽を聞いたり、恋をしたりすることを大事にしている人たちの物語」だと話していましたよね。そういうマインドを、函館で出会った人たちにも感じたとも書かれていました。
三宅:そうそうそう。パンフレットの対談でも話したけど、小説に出てくる人たちは、スゲー金がないんだけど映画を観に行ったり、花を盗んでくるけどめっちゃ大切にしたり、そこに俺は美しさを感じたんです。「それが大事だよな」って。
━━あー、生活が仕事だけに支配されていないというか。
三宅:それって、別に当たり前っちゃ当たり前の話なんですよ。だから、こうやって持ち上げて話すようなことでもない気もしつつ、でもやっぱり「戦争に反対する唯一の手段は、各自の生活を美しくして、それに執着することである」っていう言葉もありますし。自分が会った函館の人たちには、それを明言なんてしないけど、そういう態度を感じました。
大変な状況だからっていって、うつむいて、一度もニコリともせず暮らしてるわけがないって思うんです。どんだけ悲しい葬式でも、直後に腹は減るし、眠くもなるし、屁が出りゃ笑うし。なんか、その感覚。普通に音楽聴くし、普通に美味しい酒飲むよねっていう、リアルな皮膚感覚みたいものに対して素直な人が多いなって。それが肌で感じられたのがよかったし、そういうものが撮れればなと思いましたね。

━━主人公の『僕』を演じていた柄本佑さんは、撮影の以外のときにも街を散歩したり、函館八幡宮で台詞を覚えたりしていたと話されていましたが、三宅監督も仕事と切り離して函館を歩いたりする機会もありましたか?
三宅:どうしたって仕事と切り離せないんですが、映画に出ていただいたバー『杉の子』でも、いろんなことをやってる人と会ったし、あと、駅前の角打ちは面白かったですね。
━━えー! 駅前の角打ちって、『丸善 瀧澤商店』!? あそこ行ったんですか? 渋い(笑)。
三宅:俺、酒飲みじゃないんだけど、たしか北海道新聞の記者さんが教えてくれて。最初に、静雄の母親役の渡辺真起子さんが行ったら、ベロンベロンで帰ってきたんですよ(笑)。「めっちゃイイ店あったよ!」って。
━━(笑)。あそこのお店に行ってベロンベロンになるの、よくわかります。
三宅:その後、(柄本)佑と、(染谷)将太と、(石橋)静河の3人で行ったら、やっぱりめちゃくちゃ楽しかったみたいで。
━━あの立ち飲み屋に、『きみの鳥はうたえる』のメインキャスト3人が(笑)。
三宅:それで俺も行ってみたいなと思って、将太は東京に戻っちゃってたんだけど、佑と静河と3人で行ったら、地元のおっちゃんたちと一緒に国会議員の方が飲んでたりして。「なんでここに?」って(笑)。
━━国会議員の方! 僕も、あの店で会ったことあります(笑)。
三宅:その方も店に溶け込んでるし、俺らもおっちゃんたちから、あれ食べろだの何だの、めっちゃ絡まれて(笑)。そういうところで、函館の人の顔が見えてきたっていうのはありましたね。
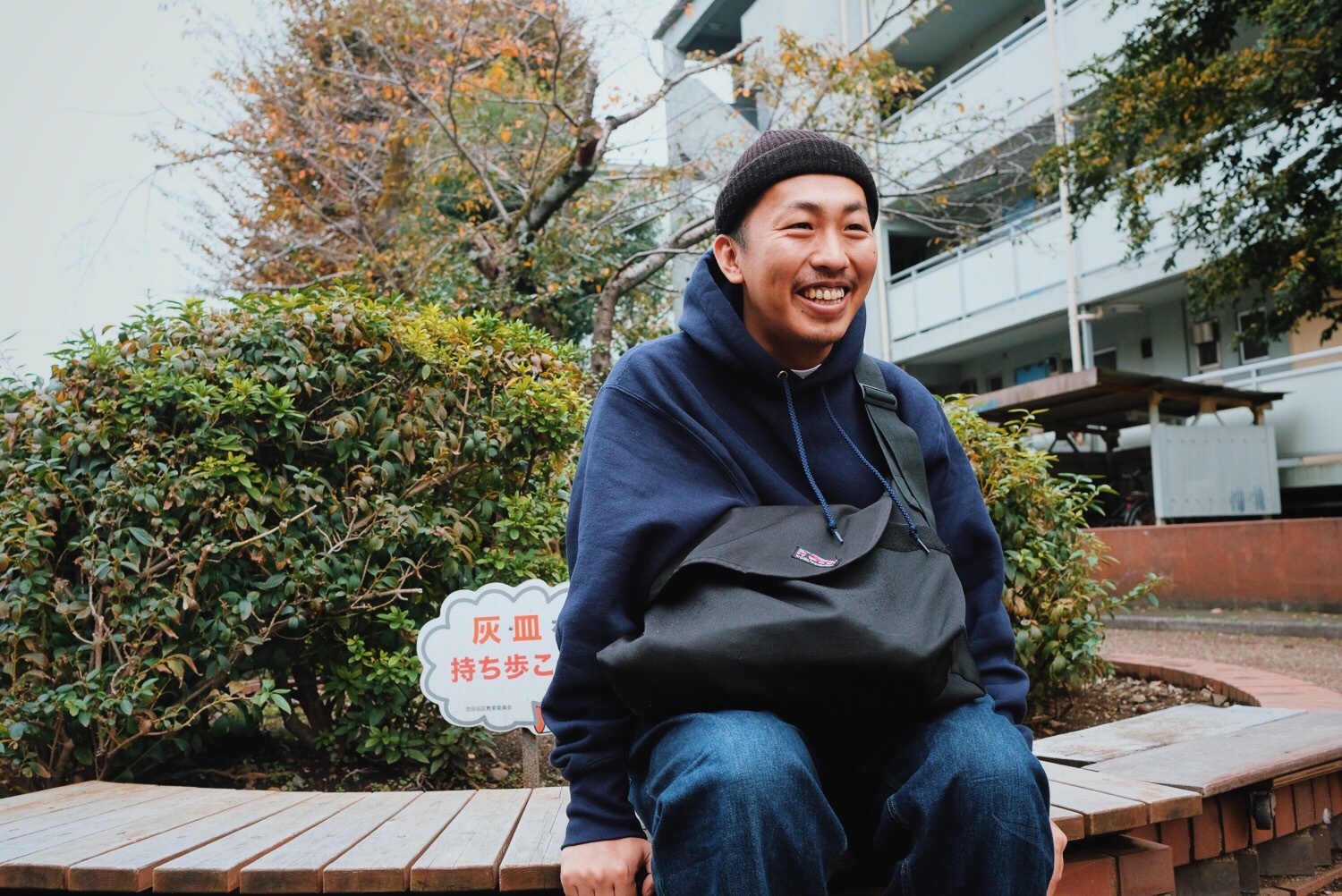
━━めちゃくちゃバカっぽい質問で恐縮なんですけど、三宅監督が肌で感じたという函館の街や人に対する印象を映像に落とし込むためには、どういう順序で、どんな作業をしていくんですか? その制作過程に興味があって。
三宅:あー(笑)。どういう順序。えーっとね、なんだろうな…。
━━感じたものをアウトプットするまでの道のりで、映画監督はどういうことを考えて、どういう作業をしてるんだろうなと思って。
三宅:えーっと…。まぁ、そもそも佐藤さんの小説に、そういうことが書かれていたといえば、そうなんですよ。函館で育った佐藤さんの感覚がまずベースにあって、それを自分なりに追いかけたんだな、と振り返って思いますね。あと、物語の話になりますけど、例えば、三角関係の中に嫉妬みたいなものがあって、メラメラっとする感情があるじゃないですか。そのメラメラが強くなっていけば、ドラマになっていくんですよ。
━━小さい火種が大きくなって、強い行動に繋がっていくってことですか?
三宅:そうそう。でも、火種をじっと見てたら、5分後には腹が減ってきたりとかして、ちょっとメラメラが弱くなることもありますよね。そこまで見てみようって思ってるんですよね。そのときに、実際の街の様子とか、実際の人の振る舞いとかを観察するのが一番参考になるんです。クラブの終わり頃とか。
━━はぁー。なるほど。
三宅:映画だと、何かが起きてガラス割れたりしても、大抵そのまま次のシーンにいくけど、現実にはガラスを掃除する時間っていうのがあるじゃないですか。
━━ありますね(笑)。
三宅:俺の好きな映画では、ガッシャーンってちゃぶ台をひっくり返した後に、「あーぁ…」ってため息つきながら、ダサい姿で片付けをするシーンとかがあったりするんですよ。それを「地に足つけて撮ってる」とか言っちゃうとかっこつけすぎかもしれないけど、そういう部分が大事だと思ってて。
━━そういう部分を丁寧に拾い上げていく作業が、一言では言い表せられない感覚を映像にしていくという制作の過程なんですかね。
三宅:シナリオを書いてるときにも、誰かと誰かが向き合っていれば、すっと温度は上がっていくんだけど、もうちょっと後まで書いてみようっていう感覚でやってます。
━━ドラマチックな結末ってわかりやすいけど、「本当は、その先もあるよね」っていうところを、三宅監督は見てるんですね。
三宅:ちょっと逸れちゃったので質問の回答に戻すと、あとは人間のドラマとはまったく無関係に、函館の街とか建物とか、光とか、いろんな人とかが存在していますよね。そういうものが、撮影のときにちょっとでもちゃんと映せれば、大きい映画になるかな、って思っています。
━━なるほどなぁ。

三宅:今の話、続けてもいいですか? 俺がよく喩えとして使ってるのは、サッカーの試合のダイジェスト映像なんですけど。あれって、ゴールシーンをメインに作るじゃないですか。だけど、「もうひとつ前のパスから見せてよ!」みたいなことってありません?
━━めっちゃありますね(笑)。「センタリング前の細いパス回しが上手かったのに!」みたいな。
三宅:そうそう(笑)。佐藤さんが書いた小説も、自分の感覚も、「サッカーの醍醐味は、スローインのボールを拾いに行ってる時間にある」みたいなところがあるなと思って。
━━その間に、ポジションが入れ替わってとか。
三宅:あいつ水飲んだせいでタイミングがズレたとか、いろいろあるじゃないですか。ゴールはもちろんあるんだけど、決めたあと爆発的に喜んで、「よし、戻ろう」っていう瞬間があるはずなんです。「まだまだ試合は終わってない。切り替えろ!」みたいな時間とか。
━━そういうところにこそ、人間らしさみたいなのが見えたりする気がしますね。
三宅:そう思うんですよね。一方で、スゲー豪華な映画っていうのは、「トム・クルーズが、やたらヤバいゴールを決めまくる」みたいな感じだと思うんです。
━━確かに(笑)! その喩え、最高だなー。
三宅:そういう映画はもちろんすごいし大好きなんだけど、今の俺たちがやれること、やれるべきことは、そういうところじゃなくて。例えば、コーナーキックのときの、ディフェンダーとフォワードのちょっとした悪口の言い合いみたいな(笑)?
━━(笑)。
三宅:そういうところにこそ何かがあるかもねっていうのが、今の自分が撮る映画の役割だなって思ってます。

━━サッカーのダイジェスト映像からは省かれちゃうような部分に面白さを見出すっていう感覚は、昔からあったんですか?
三宅:いや、そんなことはないっすね。
━━自分が面白いとか、心が動く瞬間を見つけようとしたら、そういう部分かもっていう感覚に辿り着いたんですか?
三宅:なんだろう…。映画を作りたいって思ったときに、「すごいことを思いついた!」とか思っても、もうすでに散々やられてるんですよ。たかだか120年くらいの歴史しかないジャンルなんだけど。
━━表現手法として。
三宅:表現手法もだし、物語としても。何をやっても似ちゃう。
━━「◯◯っぽいね」になっちゃうのかぁ。
三宅:そう。「だったら、もう作る必要がぜんぜんないや」って思う時期があったし、今も、「本当にやる意味あることか?」ってよく考えます。今までの映画的なルールを無視して、「新しいことやったぜ!」っていっても、とっくに誰かがやってたってほど虚しいことはないから。
だけど、「いろいろ見ていけば、まだあるじゃん。自分の足元、自分の生活の中に、まだまだ物語になってない、声になってないものはあるかも」と思ったんです。
━━既存のやり方で壁にぶつかったという経験から、発想の転換が生まれたんですね。
三宅:そうっすね。映画に憧れて、映画ごっこをするのが楽しい時期もあったけど、そうじゃなくて、映画にならなくてもいいから、自分のまわりの半径5メートルをちゃんと見るところから何かを作らないと、映画やる意味なんてないな、みたいな。

三宅:実際に映画を撮るようになってからは、〝記録の価値〟っていうのがあるってことにも気がついて。
━━記録の価値?
三宅:最初に撮った長編が『やくたたず』っていう映画で、撮影し終わったときに超絶望したんですよ。ぜんぜん思い通りにいかなくて。もっとね、アメリカの犯罪青春映画みたいなのを撮りたかったんだけど、ぜんぜんダメで。現場でも、撮影後も、マジで失敗したと思ってたんですよ。
━━えー、そうなんですか。
三宅:だけど、あの映画に赤ちゃんが出てて、編集作業に入ってから電話したら、喋れるようになってたんですよ。そのときに、「喋れなかったときの姿は、もう撮れないんだ。けど、俺は撮った」と思って。それは赤ちゃんだけじゃないよなって思ったんですよね。
━━高校生の役をやってた3人の表情や容姿だったりも、そのときにしか撮れないものですよね。
三宅:きっと、街もそう。そう考えたときに、「自分は優秀なストーリーテラーではなかったけど、何かを記録するってことは、もしかしたらできたかもしれない」って思ったんですよ。
━━二度と訪れない瞬間を。
三宅:それまで、映画っていうのは、自分の頭で考えたものを、どういう風に表現するかってことだと思ってたんだけど、そうじゃないかもって思うようになって。
「既にあって、それをどう見るか」ってことなんじゃないかなって。そうやって、記録の価値を感じるようになってからは、映画に対する考え方もけっこう変わりましたね。

三宅:時間が経てばなくなるってことでいうと、この年齢で青春映画を撮れるのは、『きみの鳥はうたえる』で最後だと思いながら撮影してました。40代、50代、60代になっても青春映画は撮れるかもしれないけど、それはもう20代の感覚とは、だいぶかけ離れたものになるから。30代半ばの今が、ギリだなって。
━━感覚的にってことですか?
三宅:そうです、そうです。当時、自分が30歳ちょいの監督だったから、『きみの鳥はうたえる』のオファーがあったんで。
━━菅原さんも、制作にあたって「まだ青春から遠くない若い監督と組んでみたかった」と言ってましたもんね。
三宅:そういうオファーだったので、だったらもう青春から遠くない者としての感覚を出すしかないなって。今後、他の映画で同じことができるとは思わないけど、今回は30代の感覚に忠実に作りました。

━━〝30代の感覚〟っていう要素を示すひとつに『僕』の衣装というのもあったと思うんですけど、柄本さんが履いていたパンツは三宅監督の私物だったんですよね?
三宅:そうですね。あれを履かせたせいで、散々言われてるんですけどね。「マジ、三宅が出てる」って。
━━(笑)。だけど、主人公の『僕』に三宅監督自身を投影した部分はあるんですか?
三宅:『僕』っていう名前の主人公に、佐藤さんがご自身を投影してたのかは正確にはわからないですけど、そう思えて。そんな小説をお借りして映画にする自分が、自分のことを一切投影しないっていうのは違うかなとは思ってて。多少は自分の人生も差し出さないと、フェアじゃないかなと思っていたので。
━━またパンフレットの話になりますけど、物語の心臓は佐藤さんの原作で、血肉は三宅監督の脚本って書かれていたのがすごくしっくりくるなと思って。
三宅:時代設定が変わるということは、つまり、お化粧は変わっちゃうわけです。でも、中身が一緒ならいいやって思ってましたね。
じゃあ、時代が変わったときの拠り所になるのは何なのかって話なんですけど、それが原作じゃないってなると、拠り所は俺たちしかないんですよ。だから、『僕』には、いわゆる衣装というものではなく、体に馴染んでる服を着てもらおうと思いました。自分たちベースの服装で。
━━それもきっと、映画を観てて主人公たちに対する勝手な仲間意識が芽生えた要因だったんだなーって、今の話を聞いてて思いました。
三宅:本当は全部、函館の古着屋とかで買えればよかったんですけどね。
━━映画を撮るときって、見る側のことも考えますか? 例えば、こういう風に見て欲しいとか、これを伝えたいとか。
三宅:それはもちろん。さっきの記録の話に近いんだけど、大袈裟にいうと〝人生は1回しかない〟っていうことですね。その1フレーズに、いろんな感情が詰まってると思っていて。その感覚を大きくするってことができれば、いいんだろうなって。
━━映画を通して。
三宅:そう。たぶん、人生が2回とか3回とかあったら、写真とか撮る必要ってないと思うんですよ。映画も。
━━あー。記録して、振り返ったりする必要がないですもんね。
三宅:「絶対に同じことは起きない。でも、伝えたい」っていうのが、記録の根幹だと思ってて。
たぶん、大昔の人も、「とんでもない狩りがあったけど、もう二度と起きないから、とりあえず洞窟に絵描いておこう。こんなんだったよ!」って気持ちで、壁画とかを描いたと思うんですよ。
━━確かに、何度も何度も同じことが起きるなら、わざわざ記録には残さないかも。
三宅:「あのとき、こんな気持ちで恋をしちゃったんだ」ってのを歌にしたりとか、「かつて、こんな悪い王様がいたから、後世に伝えなきゃいけない」っていって演劇にしたりとか、そういうのって何度も同じことが再生されるんだったら、生まれないと思うんですよ。映画もきっとそういうことなんだなって思って。
具体的にいえば、俳優と俳優が向き合って、喋って、笑ったりするっていう瞬間に、同じものはない。それを記録したものを、観た人は自然とか、生々しいとか、面白いとかいろんな言葉で言ってくれるけど、俺の気持ちとしては、「これはもう、このとき1回しかない」ってことなんですよ。そういう瞬間が映っていれば、きっとお客さんはいろんなことを考えてくれるかなって。

━━さっきの話にあったように、映画ってひとつの記録だと思うんですけど、三宅監督が見てる映画はライブなんですね。その場限りの。
三宅:あー、その感じはあるかもなー。映画って複製芸術だから、基本的にライブ性なんてないはずなんだけど。
━━観客にはないはずですけどね。だけど、現場で撮ってる人にとって、その場で起きていることを映像に収めるっていうのは、ライブ的な行為ですよね。
三宅:そう思う。それと、今はもう上映フォーマットがデジタルになっちゃったけど、フィルムだったときは上映するたびに傷がついて、ちょっとずつ変わっていくんですよ。すごくマニアックな話だけど、実はあれはライブだったのかもしれない。でもまあ、観るってこと自体は、現場でも映画館でも、時差はあるけど同じ行為だから、上映を体験するのもライブなのかもしれない。
━━なるほどー。それ面白いっすね。

━━『きみの鳥はうたえる』でも、クラブのシーンはすごくライブ感がありますよね。あそこは30分くらいカメラを回しっぱなしで撮影したと聞きました。柄本さんも「あの時間はほぼ(撮影監督の)四宮さんとのセッションですよね」と話していたのが印象に残っています。
三宅:あの撮影で覚えているのは、まず前日に演出部で打ち合わせしてるときに、「ここって3人が、いろいろ関係が変わっていく前のシーンだから、そういうのを感じさせるような視線や動きを入れる演出でいきますか?」って話が出たんですよ。
そのとき、俺は「わ! 何も考えてない!」と思って、30分くらい考える時間をもらったんですけど、「いやいや、違う」ってなって。「クラブって、そういうのないわ。基本的にめっちゃ楽しい場所であって、それだけを撮りにきたんだ」と思って、「演出プランは特にないっす」って言ったんです。
━━(笑)。
三宅:「いや、あるんだけど、基本的にはクラブは楽しいってことだけ記録します」ってことにして。バリバリに分析的に演出して撮る場所じゃないから、現場の空気次第でちょっとずつニュアンス作るわって。とにかくまず音楽があって、それによって嫌なことを忘れられる時間みたいなものだけ映像として定着すれば最高だなって思ってましたね。
━━まさにライブですね。
三宅:ですね。クラブのシーンを撮らせてもらった『STONE LOVE』の階段を下りて行くときに、佑が「俺、クラブとか初めてなんですよ。すいません、今さら。何すればいいんでしたっけ?」って言ってきて。
━━はい、はい。
三宅:それで、メインの3人に「目的はもう、楽しむだけ」って伝えたんです。「めっちゃいい音楽が流れるから、酒飲んで、楽しんでればいい! たぶん、俺もずっとそうしてるから」って。
━━自然な姿を撮るための演出ではなく、「ただ楽しむ」っていう姿勢が、あのライブ感を生んだのかぁ。

━━ちょっと話が逸れるんですけど、クラブのシーンに僕の友達が何人か映ってて。
三宅:マジっすか! それは本当にありがとうございます。どの辺にいた人ですか?
━━たしか、白っぽい服を着て、フロアの脇の方にいたと思うんですけど。
三宅:あ、じゃあ、静河が踊ってたときに近くにいた人かな?
━━そうです、そうです!
三宅:あの人? いやぁ、よかったなー、あの人。いろんなところで、よく言われるんですよ。「あそこで佐知子を見てる男、クラブにいるときの俺なんすよ!」って。
━━あー、自分を投影して(笑)。
三宅:そうそう。全国にあの人がいたんですよ! よろしくお伝えください(笑)。




